制度・環境・文化
Culture
Concept 「こどものいる生活提案企業」という想い
私たちは子育て支援を育児や保育と言う限局的な意味ではなく、こどもがいることによる生活様式(文化)全般と位置づけ、こどものいる生活がより豊かなものになるような実践と情報発信・提案を行うことで、少子化の流れを減速させ、出生率を向上させることを目指しています。

hugの精神
hugくむ保育園のhugは「ハグする」のhugです。色々な人にハグをしながら旅をした人の話に由来しています。
今でこそハグをすることの心理的効果は沢山の研究で示されていますが、前述の旅人はそんな効果など知らなかったと思います。
その旅人は
〇尊敬を持つこと
〇条件をつけないこと
〇心からすること
〇感謝をこめること
〇瞬間を大切にすること
を意識してハグをしていたそうです。
弊社ではこの「尊敬を持つこと」「条件をつけないこと」「心からすること」「感謝をこめること」「瞬間を大切にすること」に共感し、これを【hugの精神】と呼び、職員の行動規範とするとともに、hugくむ保育園に通うこどもたちにもそんな大人になってほしいという願いを込めて園名にしています。
今でこそハグをすることの心理的効果は沢山の研究で示されていますが、前述の旅人はそんな効果など知らなかったと思います。
その旅人は
〇尊敬を持つこと
〇条件をつけないこと
〇心からすること
〇感謝をこめること
〇瞬間を大切にすること
を意識してハグをしていたそうです。
弊社ではこの「尊敬を持つこと」「条件をつけないこと」「心からすること」「感謝をこめること」「瞬間を大切にすること」に共感し、これを【hugの精神】と呼び、職員の行動規範とするとともに、hugくむ保育園に通うこどもたちにもそんな大人になってほしいという願いを込めて園名にしています。
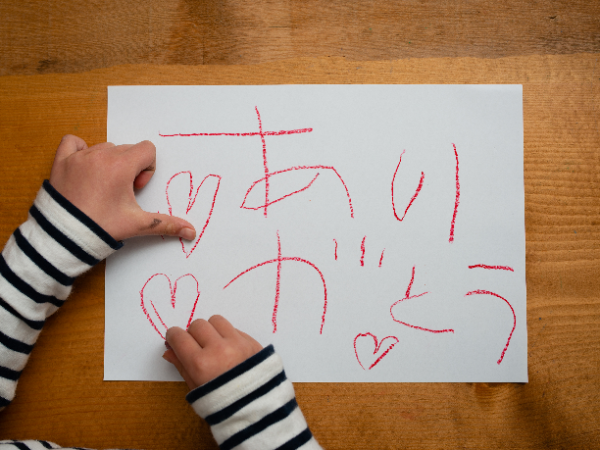
こ・そだちの社風
私たちは子育ての「楽しさ」をお伝えする会社です。
そんな会社である以上、誰よりもこ・そだちで働く人が「楽しく」人生を送れなければいけないと考えています。
〇「お互い様」の精神
弊社には小学生以下のお子さんがいるスタッフも複数在籍しております。子育てをしていると、お子さんの体調不良や学校行事、様々な理由でお休みしなければならないことがあると思います。そんな時でも安心。職員全体でフォローしあう「お互い様」の精神は長年の積み重ねで根付いています。
〇人間的な成長を促す職務グレード
人事考課ではなく、上司と部下のコミュニケーションツールとして弊社独自の職務グレードがあります。職務グレードをもとに年に2回、個別面談を実施しています。内容は保育の技術・知識ではなく人間力に焦点を当てているので、経験や年齢に関係なく、自分の長所や次の課題を見つける機会となっています。
〇業務効率化
私たちはNO残業・NO持ち帰りを目指しています。その為には業務の効率化は必須です。一人ひとりが今抱えている業務を主任が常に把握し、時間調整を行いながら、デスクワークや製作に充てる時間を作っています。
〇絵本コンクール
毎年の恒例行事として絵本コンクールを行っています。テーマは毎年変わります。先生たちの個性・感性が見え、とても楽しいイベントです。毎年、出品する強者もおります。
そんな会社である以上、誰よりもこ・そだちで働く人が「楽しく」人生を送れなければいけないと考えています。
〇「お互い様」の精神
弊社には小学生以下のお子さんがいるスタッフも複数在籍しております。子育てをしていると、お子さんの体調不良や学校行事、様々な理由でお休みしなければならないことがあると思います。そんな時でも安心。職員全体でフォローしあう「お互い様」の精神は長年の積み重ねで根付いています。
〇人間的な成長を促す職務グレード
人事考課ではなく、上司と部下のコミュニケーションツールとして弊社独自の職務グレードがあります。職務グレードをもとに年に2回、個別面談を実施しています。内容は保育の技術・知識ではなく人間力に焦点を当てているので、経験や年齢に関係なく、自分の長所や次の課題を見つける機会となっています。
〇業務効率化
私たちはNO残業・NO持ち帰りを目指しています。その為には業務の効率化は必須です。一人ひとりが今抱えている業務を主任が常に把握し、時間調整を行いながら、デスクワークや製作に充てる時間を作っています。
〇絵本コンクール
毎年の恒例行事として絵本コンクールを行っています。テーマは毎年変わります。先生たちの個性・感性が見え、とても楽しいイベントです。毎年、出品する強者もおります。

私たちの文化
『楽しい』と『HAPPY』
私たちの行動の基準は「楽しいか・HAPPYか」です。
「楽」と「楽しい」は違います。誰かに言われたこと、決まっていることだけをやるのは確かに「楽」ですが、それは「楽しい」ではありません。
自分が「やりたい!」と思える保育や仕事を提案し、実践し、それが結果につながることが「楽しい」という意識で仕事をすることを心がけています。
もう一つが「HAPPYか」。
仕事の目的は自分の人生をHAPPYにすることだと考えています。そして自分だけではなく自分に関わる全ての人がHAPPYになることが大切です。一人で頑張ることが必ずしもHAPPYであるとは限りません。時には周りの人に協力してもらうことも、実は周りの人をHAPPYにすることに繋がります。
「自分はHAPPYか?」「周りもHAPPYか?」を常に意識することを一人ひとりに根づかせたいと思っています。
私たちの行動の基準は「楽しいか・HAPPYか」です。
「楽」と「楽しい」は違います。誰かに言われたこと、決まっていることだけをやるのは確かに「楽」ですが、それは「楽しい」ではありません。
自分が「やりたい!」と思える保育や仕事を提案し、実践し、それが結果につながることが「楽しい」という意識で仕事をすることを心がけています。
もう一つが「HAPPYか」。
仕事の目的は自分の人生をHAPPYにすることだと考えています。そして自分だけではなく自分に関わる全ての人がHAPPYになることが大切です。一人で頑張ることが必ずしもHAPPYであるとは限りません。時には周りの人に協力してもらうことも、実は周りの人をHAPPYにすることに繋がります。
「自分はHAPPYか?」「周りもHAPPYか?」を常に意識することを一人ひとりに根づかせたいと思っています。

研修制度
〇新人研修
・ルーティン業務研修
入社したばかりは右も左も分からないと思います。
出勤から退勤までの1日の業務の流れなどを学ぶ研修となります。
・理念研修
会社や保育園は一つの「船」だと思います。
船の行き先や船長の考え、人柄が分からない船には不安で乗船できないと思います。
会社の方向性や経営理念、社長の方針、保育理念や園長先生の考えなど、ワークも交えながら理解を深めていく研修です。
〇基礎研修
・事例検討
主役は発表者となった保育士!内容やまとめ方については上司先輩のサポートがあります。
発表者にとっては自分の保育を整理するきっかけとなり、参加者にとっては発表者が体験した事例からの学びが、自分の保育に対する気づきのきっかけとなっているようです。
〇外部研修(基礎編)
保育士会主催の研修会や手遊び歌、読み聞かせ、運動遊び、病気、アレルギーなど個別の内容の研修に参加することができます。
〇外部研修(応用編)
社員以上になるとより専門的なキャリアップ研修やフィンランド式キッズスキルといった専門的な幼児教育の研修に参加することができます。
またマネジメント研修、コミュニケーション研修など、園長や主任に求められるマネジメントに必要な研修にも参加することができます。
〇合同研修発表大会
年に2回、姉妹園と合同で合同研修発表大会を開催しています。
同一内容の研修に複数人で参加していただくことは難しい為、研修に参加した職員がその内容をまとめ、他の職員に共有する貴重な時間です。外部研修で学んだ知識・技術を他の職員に共有することができ、発表する職員も再度、学んだことを整理する機会になっています。
☆私たちの仕事はエンドユーザーである子ども・保護者とダイレクトで向き合う仕事です。また複数の職員で協力して行うことが必須の仕事です。
保育技術・保育知識を学んでいくことはもちろん大切ですが、人間相手の仕事である以上、まず学ぶべきは人間力だと考えています。
勿論、職員一人ひとりがそれまでの人生で経験して積み重ねてきた人間力は大切ですが、私たちが携わる人の数だけ、想いや個性があります。
そんな多くの人とお仕事をする為には自らの人間力に加え、それにさらに磨きをかける、あるいはもっと豊かにする研修や経験が必要だと考えています。
hugくむ保育園で働くスタッフには、様々な経験や研修を通して、「素敵な人」になってほしいという想いがあります。
・ルーティン業務研修
入社したばかりは右も左も分からないと思います。
出勤から退勤までの1日の業務の流れなどを学ぶ研修となります。
・理念研修
会社や保育園は一つの「船」だと思います。
船の行き先や船長の考え、人柄が分からない船には不安で乗船できないと思います。
会社の方向性や経営理念、社長の方針、保育理念や園長先生の考えなど、ワークも交えながら理解を深めていく研修です。
〇基礎研修
・事例検討
主役は発表者となった保育士!内容やまとめ方については上司先輩のサポートがあります。
発表者にとっては自分の保育を整理するきっかけとなり、参加者にとっては発表者が体験した事例からの学びが、自分の保育に対する気づきのきっかけとなっているようです。
〇外部研修(基礎編)
保育士会主催の研修会や手遊び歌、読み聞かせ、運動遊び、病気、アレルギーなど個別の内容の研修に参加することができます。
〇外部研修(応用編)
社員以上になるとより専門的なキャリアップ研修やフィンランド式キッズスキルといった専門的な幼児教育の研修に参加することができます。
またマネジメント研修、コミュニケーション研修など、園長や主任に求められるマネジメントに必要な研修にも参加することができます。
〇合同研修発表大会
年に2回、姉妹園と合同で合同研修発表大会を開催しています。
同一内容の研修に複数人で参加していただくことは難しい為、研修に参加した職員がその内容をまとめ、他の職員に共有する貴重な時間です。外部研修で学んだ知識・技術を他の職員に共有することができ、発表する職員も再度、学んだことを整理する機会になっています。
☆私たちの仕事はエンドユーザーである子ども・保護者とダイレクトで向き合う仕事です。また複数の職員で協力して行うことが必須の仕事です。
保育技術・保育知識を学んでいくことはもちろん大切ですが、人間相手の仕事である以上、まず学ぶべきは人間力だと考えています。
勿論、職員一人ひとりがそれまでの人生で経験して積み重ねてきた人間力は大切ですが、私たちが携わる人の数だけ、想いや個性があります。
そんな多くの人とお仕事をする為には自らの人間力に加え、それにさらに磨きをかける、あるいはもっと豊かにする研修や経験が必要だと考えています。
hugくむ保育園で働くスタッフには、様々な経験や研修を通して、「素敵な人」になってほしいという想いがあります。






